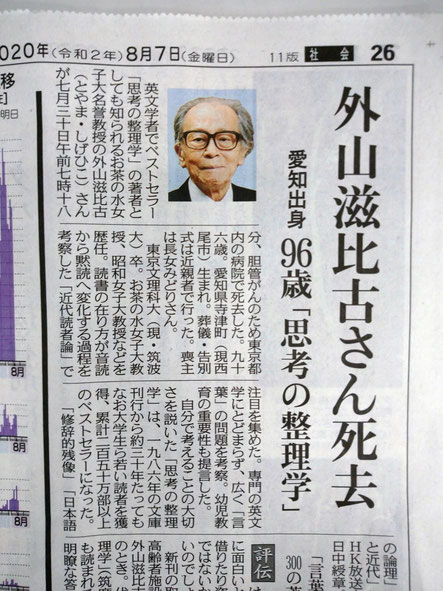お寺での修行僧は上が80歳、下は小学5年生だった。私と同世代の高校生もいた。
小5の男子は朝5時の起床に難があり、いつも眠そうな顔で読経していたが、本堂での朝のお勤めに遅刻することは一度もなかった。このことはとてもすごいことだと思い感心した。体は大きくはなかったが精神面がとても強かった。11歳で故郷長野から愛知県の岡崎市にたったひとりで僧侶の修行に来ているのである。親元を離れ異郷の地での生活だ。それも普通の生活ではなく、寺に住み込みでの修行なのだ。私よりも数か月はやくこの寺に入山したので、私は小5の彼を「先輩」と呼んでいた。私の方が入門が遅いのだから当然である。だが入浴に関しては私が一番風呂だった。8時から夜のお勤めが始まるのだが、私だけはそれをせず、その時間から学校の勉強をするように住職から申し渡されており、午後7時半に入浴せよとなっていた。これは修行僧の方々に対して礼を逸するのでは?と辞退したのだが、「入浴せよ!」ときつく言われたので最終的にそれに従ったが、このお寺で一番末席の私が一番風呂に入ることへの抵抗感がずっとあった。身分不相応に思えた。が「先輩」に「お風呂の湯加減、どうかなぁ?」と聞かれて、熱いとかぬるいという、いわば温度センサーが私の役目だった。ここのお風呂は今ではほとんど見かけなくなった「五右衛門風呂」で、大きな釜というか「はそり」というか、中に貯めた水を薪でたきつけて直接沸かす風呂なので、やけどしないように円形のざら板に乗って入浴しなければならなかった。約15分間の入浴中に格子の外で、湯加減の微調整を彼が毎日していた。
彼は9歳で出家した。小学3年生で出家し、実家のお寺で2年間すごし、小5でこの寺に来た。ここで約2年修行したら一度実家に戻り、その後また別のお寺での修行が続くんだと私に教えてくれた。すごいと思った。これはすごいことだと思った。わずか9歳で自分の将来を決定し、目標を定め、手段を特定し、それを毎日毎日地道にコツコツと積み上げていく。それをすでに2年間も継続している。しかも今は親元を離れて。親の思いや本人の覚悟を考えたとき、その強固な意志に基づく修行という貴い生活は、シンプルでありながらとても力強いものだと思えてきた。
それに比べると、何て自分は弱い生き方をしているのか?だんだん恥ずかしくなってきて、彼によって用意された風呂に入らせていただくことは、とても畏れ多いことに思えてきた。16歳の私は弱く、11歳の彼は強かった。やはり彼は私の先輩で、尊敬すべき小5の修行僧だった。私の、その足らない覚悟を、彼をしっかりと見て、学んで、私の足らないところを補っていかなければならないという思いが、入浴するごとに強くなっていった。(つづく)
 特進サクセス ホームページ
特進サクセス ホームページ